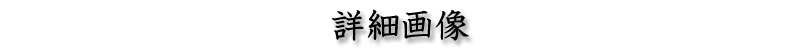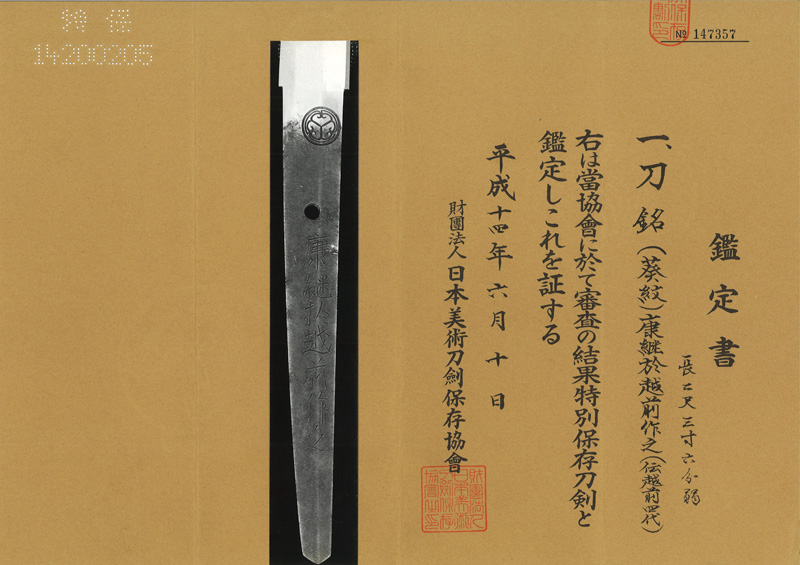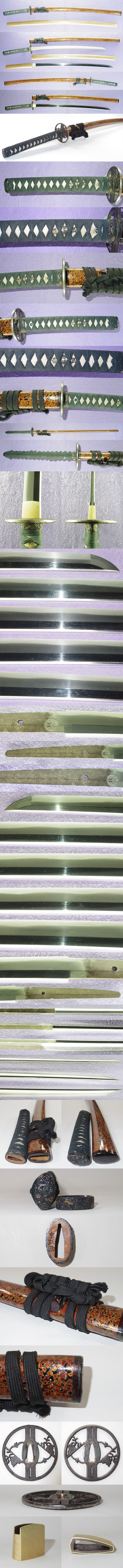|
日本刀 刀 (葵紋) 康継於越前作之 (伝越前四代)
katana (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (den echizen yasutsugu 4 generation)
|
| 日刀保 特別保存刀剣 NBTHK Tokubetsu Hozon |
品番:2310-1011 |
| 青貝微塵津軽塗鞘打刀拵付き 白鞘入り |
| 刃長 Blade length(HA-CHOU) | 71.5cm (二尺三寸六分弱) |
| 反り Curvature(SORI) | 1.1cm |
| 元幅 Width at the hamachi(MOTO-HABA) | 3.14cm |
| 元重 Thickness at the Moto Kasane | 0.74cm |
| 鎬重 | 0.76cm |
| 先幅 | 2.22cm |
| 先重 | 0.50cm |
| 茎 | 生ぶ | | 国 Country(KUNI)・時代 Period(JIDAI) | 越前国 : 江戸時代中期 元禄頃 (1688-1704)
echizen : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704) |
|
| 登録 |
静岡 第11514号 昭和29年10月26日 |
| 鑑定書 |
公益財団法人 日本美術刀剣保存協会 特別保存刀剣鑑定書 平成十四年六月十日 |
|
|
【コメント】
初代康継の生国は近江国下坂村で美濃国千手院の後裔という。
初銘を越前下坂と切り、後に越前にて北ノ荘藩主結城秀康(徳川家康次男)のお抱え鍛治となり、
秀康の推挙により将軍家御用鍛治となり徳川家康より「康」の字を賜って康継と改銘し葵紋を中心に切ることを許された。
康継(越前三代) (四郎右衛門)は初代康継の三男で、即ち二代康継の弟です、二代康継没後にその実子(江戸三代康継)との間に康継家の相続争いがおこり、
江戸康継家と越前康継家にわかれ、それぞれ三代康継を襲名しました、越前康継家を創立したのが越前三代康継(四郎右衛門)です。
江戸では江戸三代を継いで以降十二代まで続き、越前に於いては『四郎右衛門』が越前三代となり九代まで続く。
越前康継家の名跡は四代吉之助(元禄頃)、五代武右衛門(享保頃)、六代武右衛門(宝暦頃)、七代四郎右衛門(寛政頃)、八代市左衛門(文化頃)、九代市之丞(文久頃)、
と連綿と続きました。
|
販売済
Sold
|
|
|
|